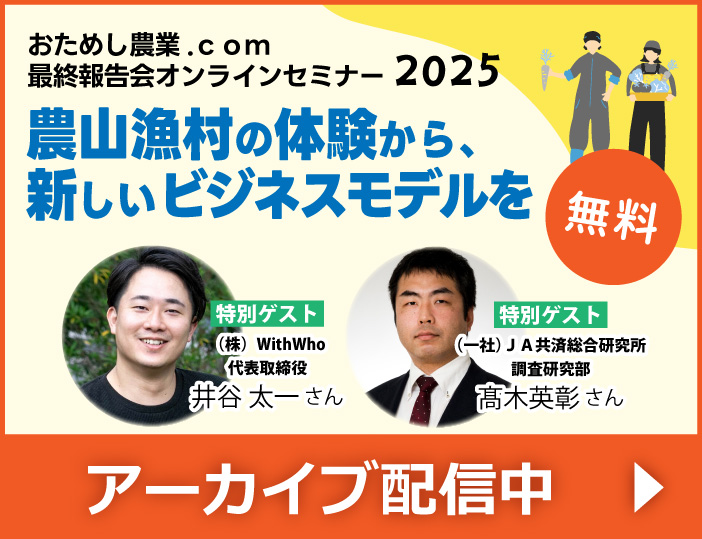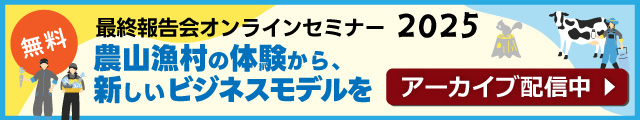~研修事業者はどう取り組んだか~
~研修事業者はどう取り組んだか~農林水産省の農山漁村振興交付金制度を活用した関わり創出事業は、2022(令和4)年から24(同5)年の3年度にわたり実施された。
当シリーズでは、関わり創出事業の大きなテーマである研修後の自走化にあたり、研修事業部門の採択を受けた事業者がどのように取り組んだかについてレポートする。
2回目は、2022年度から2年間、研修事業者として全国各地での研修を主催したNPO法人サービスグラント にスポットを当て、自走化にどう取り組んだかを同社からの報告を基に紹介する。
非営利活動法人サービスグラントの紹介
サービスグラントはNPO活動を支援する中間支援型のNPO法人で、プロボノ(職業を通じて培った経験やスキルを生かして、社会課題の解決に寄与する活動のこと。ボランティアの一種)として、活動したい人とサポートを必要とする団体とをつなぐ役割を担う。
活動自体は2005(平成17)年から始まり、これまでに約9700人がプロボノとして登録し、約1900件のプロジェクトを進めてきた。グラントは英語で「助成(金)」という意味があり、団体名の「サービスグラント」は資金ではなく「サービスによる助成」という意味である。経験やスキル、専門知識など資金とは違う支援を、社会活動に取り組む団体に提供している。
関わり創出事業での取り組み内容
サービスグラントは、中間支援組織としてNPOや地域団体に社会人のスキルを生かしたボランティアを通じて関わってもらう「プロジェクト型支援」を東京、大阪を中心に実施してきた。しかし、農山漁村こそ担い手が必要と考え、交付金を利用して「ふるさとプロボノ」に取り組んだ。参加者(プロボノワーカー)と地域をつなぐだけでなく、地域が自らプロジェクトを掲載し外部人材を募集できるよう、オンラインプラットフォーム「GRANT(グラント)」(https://grant.community/)を中間支援組織や自治体の第1次産業振興・関係人口創出の担当部署、観光協会に提供し、これまでつながりのなかった全国のコーディネーターと連携。活動団体の支援に取り組んでいる。

「ふるさとプロボノ」活用の地域組織のワークショップにオンラインで参加するプロボノワーカー(丹波篠山市)
関わり創出事業で実施した研修の取材記事一覧
漁業と漁師の魅力を掘り起こす―広島県福山市内海町 | おためし農業.com
清流と緑のまちで地域の魅力を発信―佐賀県唐津市厳木町 | おためし農業.com
「獣がい対策応援消費」を支援 兵庫県丹波篠山市 | おためし農業.com
サウナで島を盛り上げる 島根県隠岐の島町 | おためし農業.com

漁業の研修を終え港に戻ってきたプロボノワーカーの皆さん(手前3人:福山市内海町)
自走化に向けて
自走化に向けては、関わり創出事業終了後、以下の三つのアプローチで進めている。
〔1〕ツールやノウハウの提供
「人がいないから何もできない」と考えている行政担当者や地域おこし協力隊員ら向けに、「思いがあればそれを発信していつでも人を確保できる」環境として、GRANTの無償提供や、プロジェクト型でつながるためのノウハウを共有。
〔2〕企業との連携・協働
企業の社会的責任(CSR)や人材育成の観点から、地域課題に社員が関わる経験や機会を求める問い合わせが増えており、研修事業の2年間でつながりのできた地域で社会課題解決型越境学習プログラム「プロボノリーグ」(複数社乗り合いでチームを作り、地域支援の成果物を納め提案する)の実現にチャレンジしている。
〔3〕事務課題解決支援(ジムボノ)
地域が活用できる国の施策は多いが、事務回りに割ける人材がいないことで諦めてしまうことがよくある。企業勤めだと基礎的に事務能力が備わっている人が多く、事務負担の軽減を担うコアな関係人口を地域につなぐ新しい取り組みができないか検討中。地域のニーズとして「補助金事務の効率化」が根強くある。「中山間地域等直接支払制度」などの各種直接支払制度について学びながら、事務をサポートできる人材の育成とマッチングを広げていきたい。
取り組んでみた感想、今後の展望
GRANTを運用したところ、「情報発信」「マーケティング」「ICT活用による業務改善」が代表的な地域ニーズであることが分かった。これらの課題は目標と期間を決めてプロジェクトとして設定すれば外部から手伝ってくれる人はやはり多いと感じており、プロジェクト化の手法や実施方法を地域の関係者に伝授するための導入研修の費用を地域から提供してもらいながら、いずれは地域が自立して人材獲得できるよう、移行支援をパッケージとして提案している。
企業版プロボノ
2年間、関わり創出事業に取り組んだ結果、参加者の9割以上が一般的なビジネスパーソンであることが分かった。
企業側では社会貢献はこれまで優先順位の高い位置付けではなかったが、昨今はSDGsやESGに向けた取り組みとして関心が高く、サービスグラントとして伸ばしていく領域である。また、企業にオープンイノベーション(外部の技術やアイデアを取り入れ、新しい価値を生み出す)の可能性を見据えたいという意識もあることから、1プロジェクトに1社という形の農村研修・社会貢献だけではなく、「プロボノリーグ」を開催した。プロボノリーグはこれから特に注力していきたい企画である。
また、長崎県とプロボノ協定を結んでおり、県としては地元の中小企業や経済界を巻き込みながらNPOの支援や地域課題の解決につなげたいので、「企業×プロボノ」という発想で何ができるかを検討している。このような形で行政と協働したプロボノ事業として、地域内外の資源を取り込みながらふるさとプロボノを実施していくシナリオも見えてきた。

プロボノワーカーがワークショップを進行し、地元の人と地域課題の解決を図る(隠岐の島町)
収益化の取り組み
2024(令和6)年7月には広島県三段峡のNPOへの支援活動として、終日の研修・現地滞在プログラムを実施した。こうした企画で人材を送り出した企業から研修参加費を受領し、これを基にプラットフォーム「GRANT」を拡充、さらに参加者が増加するという循環を強化していきたい。
関わり創出事業の実施効果
創出事業に取り組み、サービスグラントに残った最も大きなインパクトは、事業に関わった人材がサービスグラントに加入したこと。佐賀県唐津市の旧厳木町で地域支援員としてプロジェクトの受け入れ窓口になっていた横道亨氏が、サービスグラントのメンバーとなった。横道氏は九州地域でのプロジェクト拡大に取り組み、NTT東日本など新しい企業と連携しながら、佐賀県を中心にプロボノリーグの九州地方での展開を模索している。
取材記事参照 https://otameshi-agri.com/editorial-index2023/editorial6/

JR唐津線厳木町駅前で自身が推進するプロジェクトの募金を呼び掛ける横道氏(研修時)