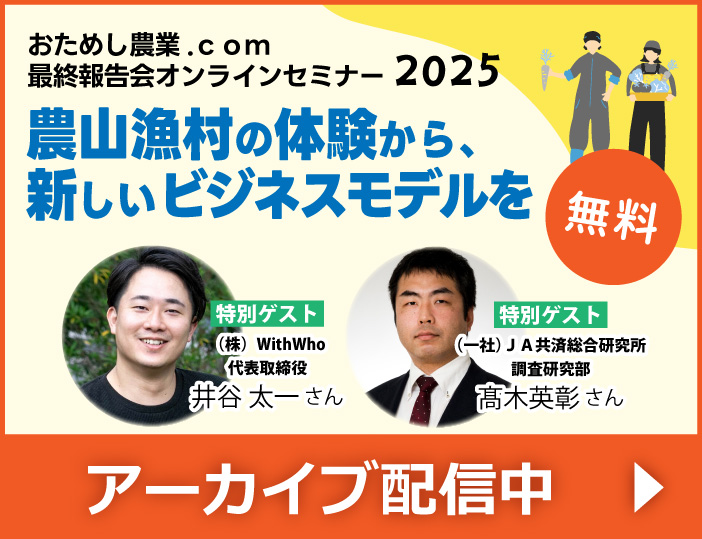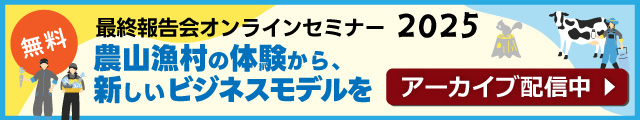~研修事業者はどう取り組んだか~
~研修事業者はどう取り組んだか~農林水産省の農山漁村振興交付金制度を活用した関わり創出事業は、2022(令和4)年から24(同5)年の3年度にわたり実施された。
当シリーズでは、関わり創出事業の大きなテーマである研修後の自走化にあたり、研修事業部門の採択を受けた事業者がどのように取り組んだかについてレポートする。“自走化”とは、交付金を活用した研修事業の終了後も研修地で経済的に自立した事業活動が持続し関係人口を継続して創出することで、当事業の最終的な目的である。
3回目は、2022年度から2年間、研修事業者として全国各地で研修を主催したハレノヒ株式会社 にスポットを当て、自走化にどう取り組んだかを同社からの報告を基に紹介する。
ハレノヒ株式会社の紹介
設立は、2013(平成25)年。農業の分野で、主に地方都市の活性化や人口減少・経済活動の問題、基幹産業の衰退といった地域の課題に対して、市場の拡大や新たな用途開発など、これまでの手法を刷新し、新しい価値を生み出し解決していくという取り組みを行っている。現在は中山間地域の農業に特化して、コンサルティング事業にとどまらない複合的な事業を実施している。
関わり創出事業での取り組み内容
同社は地域の課題解決を目的としており、その手段として外部人材による外側からの視点や特殊技能・特異性を生かし、新たな地域資源を創出。また、その価値を創造しようと創出事業に取り組んだ。
地方都市では人材・労働力不足が深刻になっており、創出事業を通して改めてそのことを明確に認識した。労働力不足の問題に関しては、都市部にしかいないような人材も地域では非常に重要視されており、そうした人々を取り込みながら地域課題を解決することを2年間取り組んだ。
現在も各地での取り組みは継続しており、AI導入、販売促進、魅力の創出、移住・定住などのテーマで定期的な訪問を推進している。現在、力を入れているのは、地域資源の付加価値化のための6次産業化や各種体験事業、そして、これらの市場拡大を目的とする海外市場への挑戦などである。

吉野杉の箸の製造工程を学ぶ研修生(奈良県吉野町)
関わり創出事業で実施した研修の取材記事一覧
以下にハレノヒが全国で実施した研修の取材記事を紹介する。
ドライフラワーアレンジメントと伝統行事を学ぶ~群馬県中之条町六合地区 | おためし農業.com
吉野杉の産地で林業を学びながら地域の課題解決を目指す~奈良県吉野町 | おためし農業.com
オホーツクの大地で1次産業を学ぶ―北海道網走郡大空町 | おためし農業.com
種子島で1次産業を学ぶ―鹿児島県種子島 | おためし農業.com

カボチャの収穫を終えて(北海道大空町)
関わり創出事業を通して感じた課題
2年間取り組んでみて、受け入れ側と研修生側のミスマッチ、受け入れ側の要望に対する研修生側の能力不足、受け入れ側の課題や解決策の未整理、研修生側の課題に取り組む積極的姿勢が弱い、後押ししてもなかなか解決に向かって進んでいない、という状況が見られた。
現在の自走化の活動状況
各地の活動状況
- 農水省の労働力確保体制強化事業を活用して大空町(北海道)と種子島(鹿児島
県)の間で繁閑差を利用した労働力の補完事業を実施している - 研修生が仲間を連れて農業アルバイトを継続的に実施している
- 中之条町(群馬県)の旧六合村では創出事業を生かして農泊の展開に向け協議を進めている
- 南阿蘇村(熊本県)では、山村活性化対策事業を活用して東京から研修生が参加する予定で準備が進んでいる
- 吉野町(奈良県)、三島町(福島県)では地域のイベントの手伝いに参加した研修生が今年も継続して手伝うことになっている
- 石垣市(沖縄県)や金武町(同)、旭川市東鷹栖地区(北海道)に関しても、オンラインで活動を継続しているほか、熊谷市(埼玉県)、大月市(山梨県)、辰野町(長野県)、高森町(同)では農業を通じた交流を継続している
- 受け入れ地域と研修生が独自に活動しているケース(研修地域が活動に納得している)や農水省の事業を活用してイニシャルコストを補填(ほてん)しながら活動するケース(事業内容が明確)の2パターンで、それぞれ自己が目指す方向に進んでいる

ドライフラワーアレンジメントの研修で手作りした作品(中之条町)

新茶の茶摘み(4~5月)に向け、葉に付いたゴミや虫を取る(種子島)
自走化の状況・課題・進展方向
ハレノヒとして自走化はできているが、満足できる取り組み内容には至っていないため、地域への定期的な訪問を通じて活動の修正やさらなる発展を図っていかねばならない。関わり創出事業では、大学・研究機関のサポートを受けながら多様な特殊能力を持った研修生に地域課題に取り組んでもらうところまでの段階だったが、今後は、地銀、企業版ふるさと納税、農水省の補助事業などによるファンドを投入し、課題解決の実践につなげ、地域が目標に向かっていけるような仕組みづくりを考案中。
関わり創出事業からの発展状況
以下の5地域では課題解決の最終章に向かっている。
〈種子島(鹿児島県)〉
サトウキビの糖度が低く砂糖の原料としての価値が低いため、高付加価値化に向けて鹿児島県および地域の協議会が共にクラフトラム酒の製造の検討を進めている
〈吉野町(奈良県)〉
吉野檜・吉野杉の高付加価値化のため、家具の製造と海外輸出を検討中
〈南阿蘇村(熊本県)〉
有機農産物(主にコメ)および赤牛の海外輸出を検討中
〈東鷹栖地区(北海道旭川市)〉
コメの大産地ではあるが知名度がないため、将来的な海外輸出の可能性を地域活動計画に盛り込んでいる
〈辰野町(長野県)〉
人口減少が著しく農用地保全が思ったように進まないため、農村RMOを検討しており、複数集落間での機能補完と農用地保全の組織化を計画している
関わり創出事業を通しての感想・課題感
研修生の質を一定水準に保つために応募時に面接をしているが、適切にスクリーニングすることは困難で、やる気がある者とない者が混じる。参加希望者全員が参加し続けることは難しいと感じている。
また、14日間の研修という拘束は募集条件としては厳しく、地域が求める人材を集めるのに障壁と考えている。そのため、14日より短期化することも検討したい。日数より、地域課題解決に向けた報告書やシナリオをつくって、どのように実践に関われるかというところを重視する方法も可能ではないか。誰でも参加できるというわけではないが、能力がある人間が参加しやすいようにする仕組みは必要と感じている。
自走化の取り組みの工夫として、地銀の支援を受け入れられる体制づくりが有効ではないか。さらに企業版ふるさと納税を活用した人材の有効活用も可能性があると考えている。