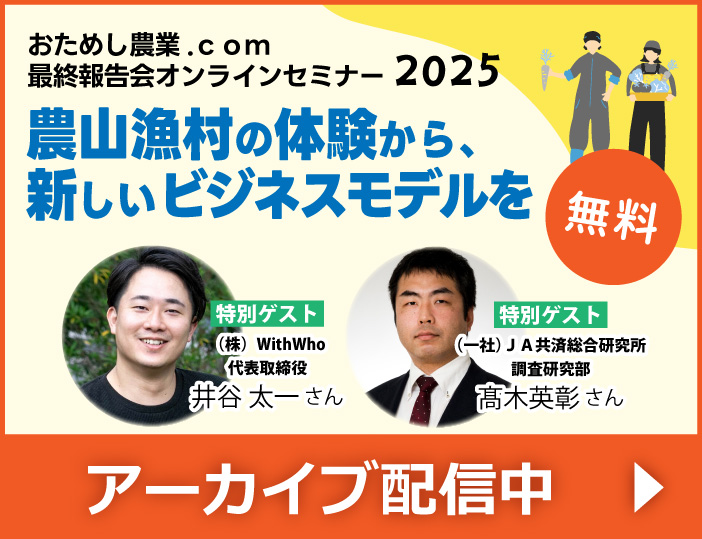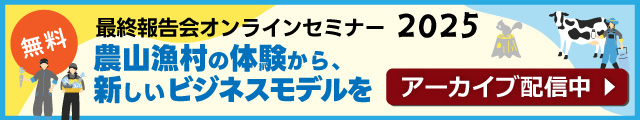はじめに
時事通信社は、農林水産省農山漁村振興交付金制度関わり創出事業の情報発信の採択を受け、2022(令和4)年度から3年にわたり、特設サイト「おためし農業.com」で研修の様子など各種の情報発信を行ってきました。この活動の総括として、情報発信の概要報告と合わせて取材を終えての所感をお伝えしたいと思います。研修事業者をはじめ研修を受け入れた各地の中間支援組織や地域コーディネーター、研修生ら関係各位に取材協力の御礼を申し上げるとともに、当記事が全国で地域再生に奮闘する地域や組織の参考になれば幸甚です。
30件の研修を取材
研修事業は全国各地で展開され、「おためし農業.com」は、北はオホーツク海近くの北海道大空町から南は東シナ海の鹿児島県奄美大島龍郷町まで30件の研修を取材し、「現地レポート」コーナーに掲載した。取材した研修に参加した人は約200人(男性、女性とも約100人)でこのうち93人の研修生に個別インタビューを実施した。

カボチャの収穫を終えて(北海道大空町)
現地レポート以外の記事について
「おためし農業.com」では、各地で実施された研修の様子を取材した「現地レポート」以外に以下の特集を展開した。
①「関係人口創出の先進事例」(全国6組織の成功事例を取材)
先進事例 | おためし農業.com
②「研修事業者の自走化の取り組み」(研修事業者がどのように自走化に取り組んだかを報告)
研修事業者の取り組み | おためし農業.com
③「2022年度の研修生の動向」
【連載4】2022年度の研修を振り返る~総括・分析編 | おためし農業.com
④「2023年度の研修生の動向」(研修時の個別インタビューから傾向を分析し、総括)
【連載4】2023年度の研修を振り返る~総括・分析編 | おためし農業.com
④「研修生の今を追う」(研修後の5人の研修生の動きを追った)
編集長コラム(令和5年度) | おためし農業.com
編集長コラム | おためし農業.com
研修生の年代は20代から60代
研修には20代から60代の幅広い年代の人が参加した。20~30代の若い世代の比率が高く、農村の高齢化が進む中で多くの若い人が農村を志向していることは心強く感じた。また実施年度ごとに地域と関わり、地域課題の解決に積極的に取り組もうとする研修生の割合が増えた。

リンゴの葉積みに励む研修生(飯島町)
研修の現地受け入れ先の業態
各地の研修の受け入れ先の業態は、自治体関連が4割、農家関連が4割、NPOや地域商社、地元メディアなどが2割という内訳だった。受け入れ先が農家の場合は農業研修のメニューが充実しているなど、研修プログラムはそれぞれの業態の持ち味が発揮されていた。
研修の取材を振り返り改めて認識したこと
◎コロナ禍を経て、地方への移住または二拠点での生活を検討する首都圏の若い世代が増加しており、農村や地域と地域外の人をつなぐ中間支援組織の役割はますます重要となる。
〈参考〉国土交通省が2024(令和6)年6月18日に発表した首都圏白書によると、東京圏在住者を対象にした調査で、20代の44.8%が地方移住に関心があると答えている。
◎中間支援組織が元気で力があるところは地域も元気であり、元気な中間支援組織には共通する要件がある。この要件は、元気な農家や農家集団にも当てはまる。
元気な中間支援組織に共通する要件とは?
【1】ビジネス的視点、営業力がある(経済的な自立ができている)
以下に研修受け入れ先の関連コメントを紹介する。
A.「自分たちは零細企業だという意識を持ち、起業すれば普通にやるべきことをやってきた。収益化が最も大事」(かまいしDMC・河東英宜社長)
B.「農業は売り先が大事。どこに直接販売するかを決めて野菜を作る」(田切農産・紫芝勉社長)
C.「売り先あっての農業なので商品を切らさないよう多品種を栽培、販売」(平塚市農家・末永郁〈かおる)さん〉
D.「農家は頭が良く健康で、3キロ以内に売り先を持ち、

平塚市の研修で野菜栽培の説明をする末永さん(左から2人目)

北海道大空町の株式会社「大地のMEGUMI」は、近隣の野菜選果場や加工場から無料で提供を受けた野菜くずを麦稈(ばっかん)に混ぜ、自然発酵で年間1000トンもの堆肥を作っている。
【2】実務、事務的能力がある(組織運営力があり、公的制度を活用)
A.組織を実務的に動かせる。
B.申請書作成など事務処理力がある。
中山間地域等直接支払制度や農村RMOなどの国や地方自治体の公的制度への申請を事務に割ける人がいないため見送るケースがある。事務処理ができる人が組織内にいなければ、元自治体や企業出身者らとの連携を模索する。
【3】同じ理念や目標を持つ仲間がいる(担い手の不在を集団でカバー)
以下に研修受け入れ先の関連コメントを紹介する。
A.「1人でやる農業はきつく難しい。これからはチームでやる時代。共通言語で話せる仲間を作ってほしい」(平塚市で有機農業を推進する「いかす」社・白土卓志社長)
B.「5年後に農業者の大幅減少が見込まれ、地域の農業を守ろうと260戸の農家が株主となり会社を設立。農家の利益確保を図っている。農道の整備などは集落営農組織を設立し対応している」(田切農産・紫芝勉社長)
C.「千葉県北東部など利根川の周辺地域で100戸の農家集団を運営」(株式会社和郷・木内博一社長)

田切農産所有の大型乾燥機について説明する紫芝社長(右端)
【4】伝える力、コミュニケーション力がある
A.地域の魅力や研修メニューの趣旨を外部の人に分かりやすく説明できる。メニューの趣旨を確認したい研修生に丁寧に説明できている。
B.外部の視点がある。外部から来た人を受け入れる包容力や気持ちがある。
C.人や地域への熱い思いがある。
力のある中間支援組織がこの4点のほかにも取り組んでいる活動を以下に紹介する。
【5】SNSを有効活用
香川県三豊市の父母ケ浜(ちちぶがはま)は、同市観光交流局の職員がSNSにアップしたことで広く認知され、来訪者が年間数千人から50万人に増えた。また、市内の研修受け入れ先の荘内半島オリーブ農園は、訪問客が農園からの瀬戸内の眺めをSNSに投稿したことがきっかけでビールのコマーシャルに使われ、来訪者が激増している。SNSの情報拡販力は大きく、地域の名産品や魅力の発信に非常に有効だ。

日の入り前の干潮時の海面が鏡のように見えることから日本のウユニ塩湖と言われる父母ケ浜でポーズを決める研修生(三豊市)
【6】新しい組織を立ち上げ、運命共同体の意識を共有
新組織を設立し、ビジョンを共有することで一体感が生まれ、次への展開をスムーズにできる。特に株式会社の形態は組織の責任が明確となり、社会的な信用度が格段に上がり金融機関からの融資に有利になるなどの大きなメリットが得られる。
「おためし農業.com」の先進事例で取り上げた島根県安来市比田地区の「えーひだカンパニー株式会社」は、任意組織を経て株式会社として誕生。当地区は面積が広い上に東西に長く、二つの小学校区に分かれていた。話し合いを通して地域ビジョンを作成し、同社が中心となってビジョンを一つ一つ実現させていくことで地域に一体感が生まれた。事業の制約がなくやりやすいし、責任が明確になる。社会的な信用度も各段に上がった。

えーひだカンパニーが開発した地産食材を使った商品の数々
【7】住民が地域全員の意見や思いを知り、危機感や問題意識を共有する
地域再生に向けて活動を開始した地域では、立ち上がった組織が住民に対してのアンケートやワークショップ、説明会の実施を繰り返し行うことで、現在の住民の率直な思いや意見の確認を行った。アンケート結果は住民全員に公開され、優先度が高いものから順番に解決を図っている。
「おためし農業.com」の先進事例で取り上げた岩手県花巻市の「高松第三行政区ふるさと地域協議会」の熊谷哲周事務局長は、「約150人の行政区では全員が参加しないと事業が成り立たないため、ビジョンを作る際のアンケートも小学一年生から寝たきりのおじいさん、おばあさんまで対象に調査した。ワークショップは、8歳から85歳まで参加した」と話している。

ワークショップで実現した福祉農園。植栽しているガマズミとナツハゼはゼリーに加工し販売
島根県安来市比田地区は、地区の人口推計が2040(令和22)年に半減するという地域の存続が危ぶまれる状況に直面し、地域住民有志がプロジェクトチームを結成。15(平成27)年に「いきいき比田の里活性化プロジェクト」をスタートさせた。
最初に比田地区全体の方向性を示す地域ビジョンを作成するため、全世帯(中学生以上)を対象に個人用と世帯主用の二つのアンケート調査を実施。「10年後あなたは比田に住んでいると思いますか?」「家の農業を10年後どうしたいですか?」などの質問に約90%の回答があった。地域全体のモチベーションを高めようと、世代別や全世代を対象にワークショップも実施。集まった1469のアイデアを優先度や実現可能性などの観点から88に絞り込み、「比田地域ビジョン」が翌年完成した。ワークショップの最後に小学校の体育館で行われた全体ワールドカフェは、いろいろな世代の人をミックスさせ、顔見知りが増えるなど意義が大きかったという。
【8】地域内の資源の確認、活用、新サービスとして展開
地元や地域の資源(ソフト、ハード)を繰り返し見直し、再生を模索。また、地域や地元では当たり前のことや物、風景が、地域外や都市部の人には魅力的で有効な観光資源であることが多い。移住者や外部の人の意見も積極的に採り入れる。
高知県梼原町四万川地区活性化する「集落活動センター『四万川』」は、廃園となっていた旧四万川幼稚園の施設の内部を2018(平成30)年に改修し、地域の葬儀や会議、避難所など多目的に利用している。

四万川地区多目的施設。町内外との交流の拠点としても有効活用されている
長野県上田市豊殿地区では、江戸時代に開墾された棚田を再生し地域の核として多面的に活用しようと「稲倉の棚田保全委員会」を設立。棚田をプラットフォームとして、棚田米や酒米のオーナー制の実施、田植え、棚田キャンプ、虫送りなどのほか、稲刈りといった学校の課外学習体験を受け入れるなど多様な活動を展開し、飛躍的に関係人口が拡大している。

稲倉の棚田。1999(平成11)年に「日本の棚田百選」に認定
岩手県花巻市の「高松第三行政区ふるさと地域協議会」は、地域の景観も重要な資源という認識から、地域づくり活動が始まった2008(平成20)年以降、名勝や旧跡の整備保全にも力を注いできた。区内の平良木地域の猿ケ石川の右岸にある立岩は、切り立った岩場と茂る樹木が織り成す景観が美しいが、手前の河川敷のうっそうとした木々や草が眺望を邪魔していた。地域住民が長期間にわたる作業で取り除き、景観が復活。その景観を求めて移住する人も出てきた。特に紅葉や積雪の風景が素晴らしく、県外から観光客も来るようになった。移住者を含め、こうした地域全体で集落の風景を取り戻す活動が評価され、20(令和2)年に同協議会が第15回「住まいのまちなみコンクール」(一般財団法人住宅生産振興財団など主催)で最高賞の国土交通大臣賞を受賞している。

景観が保全されている猿ケ石川の立岩
【9】地域おこし協力隊など外部人材の活用、地域外との連携で労働力を確保
地域おこし協力隊の活躍
2024(令和6)年度の地域おこし協力隊の隊員数は約8000人で、同制度の取り組み自治体数は約1200団体。取材で訪れた岩手県遠野市、秋田県仙北市、群馬県中之条町、三重県尾鷲市、島根県隠岐の島町などで、隊員は地域を支える重要な役割を担っていた。外国人の隊員も年々増加している。
島根県安来市の地域おこし協力隊として京都から移住した野尻ちさとさんは、安来市比田地区の再生を目指して設立された「えーひだカンパニー株式会社」の立ち上げに重要な役割を担い、現在は取締役として会社運営に臨んでいる。
秋田県仙北市の地域おこし協力隊として神奈川県から移住した溝口真矢さんは、会社員を経て「starRo」の名称で音楽プロデューサー、作曲家として活躍。米ロサンゼルス在住時の2017(平成29)年に、音楽賞として世界で最も権威のあるグラミー賞の「リミックス・レコーディング」部門で、日本人として初めてノミネートされた実績を持っている。仙北市では、リトリート(自分の生き方を見つめ直す時間)を軸にした関係人口の創出を担当。
地域外との連携で労働力を確保
北海道大空町と鹿児島県種子島の農業法人などは産地間連携に取り組み、農林水産省の労働力確保体制強化事業を活用して農繁期が異なる繁閑差を利用した労働力の補完事業を実施している。
南高梅の生産量日本一の和歌山県みなべ町は、人口の減少・流出などによる梅農家の収穫時期の人手不足が課題だったが、研修事業者であるPCW Japanの島田由香代表理事が企画した都市部で働く人と同町役場や地域の梅農家・梅加工事業者が連携する「梅収穫ワーケーション」を推進。参加者は梅収穫作業を手伝うという非日常体験によりウェルビーイングが向上、農家は無償で人手不足を解消できるという双方にメリットを得られる仕組みが出来上がった。地域課題を解消しながら地域活性と関係人口創出を同時に実現することができ、2023(令和5)年は19戸の梅農家が382人を受け入れた。この取り組みは、他地域の第1次産業にも応用できるモデルだと評価され、内閣府の優良事例に選ばれている。
【10】神楽や神事などの伝統や文化が結束の核となり地域を救う
人口減少が続く地域では、継承される神楽などの伝統や文化、地域に根付いたさまざまな活動が軸となり、地域を支える力となっている。
「おためし農業.com」の先進事例で取り上げた宮崎県西都市東米良地区は、明治時代に地区内の銀鏡(しろみ)神社の氏子集落を中心に村として独立した。一ツ瀬ダム建設の影響を受け多くの地域が水没。最大4500人いた住民の多くが村外へ流出したが、日向神話に由来し1489年に創建された銀鏡(しろみ)神社に伝わる銀鏡神楽を守ろうと氏子たちが神楽の継承に尽力し地域を支えた。2020(令和2)年に地域再生を目的に設立されたNPO法人東米良創生会の石川理恵事務局長は、「地域の精神的支柱である銀鏡神社には縄文遺跡があり、当地区は山岳信仰や狩猟文化など豊かな山の恵みの中で継続されてきた集落。守りたい、残したいものがあるから変わることを恐れずに感謝の気持ちで今の環境を次の世代へつないでいきたいと思う。この思いの共有が、集落維持と形成の基本となるものだと考えている」と話す。

東米良創生会の活動拠点「東米良仁の里」。廃校となっていた旧銀上小学校の旧校舎を活用
最後に
全国を研修の取材で訪れ、人口や第1次産業従事者の減少、高齢化が著しい速度で進行している現状を目の当たりにして危機感を強く感じましたが、各地で自治体をはじめ地域再生に奮闘する組織や団体、リーダー、さまざまな形態で農山漁村と果敢に関係を持とうとする都市部の若い世代の存在とその背景を知り、厳しい日本の現状の中で光明を見る思いがしました。そして、地域と都市部の人をつなぐ中間支援組織(地域コーディネーター)の存在は、今後より一層重要度を増すでしょう。 関係人口の観点で見ると、都市部の人が複数の地域と関わることで、1人が2~3人の役割を持ち、人口の量的な減少を質的にカバーすることが期待されます。関わり創出事業は、各研修事業者の努力により多くの関係人口を生み、今も増え続けています。関係各位のますますのご清栄を祈念し、取材終了にあたり改めて長い間のご協力に感謝申し上げます。
(編集長)

-150x150.jpg)